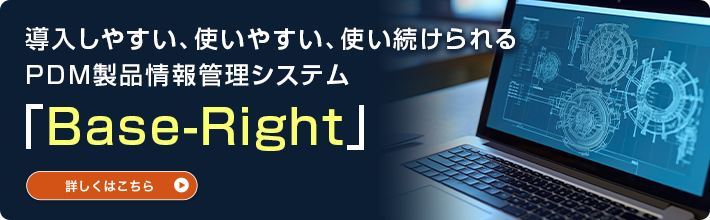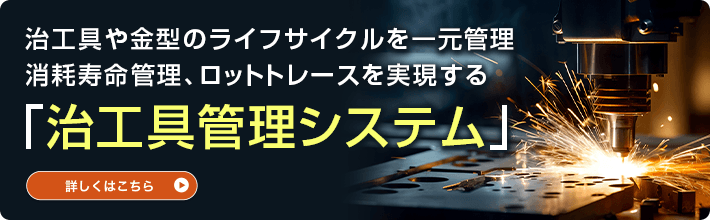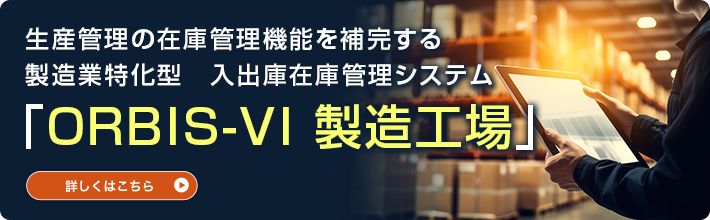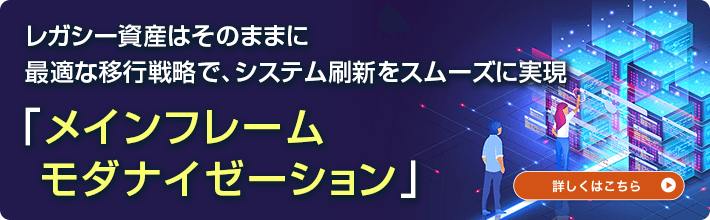製造業向け
キーワード
製造業におけるDX推進に関連した専門用語を解説しています。
製造業向けキーワード
製造業におけるDX推進に関連した専門用語を解説しています。
あ行
安全在庫
安全在庫とは、欠品や過剰在庫の発生を防ぎ、供給の安定性を確保するために保持する最低限の在庫量を指す。安全在庫を維持することは、予測不能な需要の増加や供給遅延といったリスクに対応する対応するために重要な役割を果たす。
適切な安全在庫を設定するためには需要の変動やリードタイムの不確実性、供給の安定性といった要因を総合的に分析する必要がある。また、発注点の設定により、在庫が安全在庫を下回る前に適切なタイミングで補充することが可能となり、欠品のリスクを軽減する。
エンジニアリングチェーン
エンジニアリングチェーンとは、製造業における製品の企画・設計から製造、アフターサービスに至るまでの、設計と開発を中心とした業務プロセスである。一方、サプライチェーンは調達から製造・出荷・販売までの業務プロセスのことを指す。
製品の設計では仕様書や設計図、CADデータが作成され、製造プロセスで直接使用されるため、部門間のスケジュールと情報管理が重要になる。また、近年は製品の複雑化が進んだことで効率的かつ柔軟性の高い設計が求められている。そのため、製品の情報管理を最適化するエンジニアリングチェーンマネジメント(ECM)を導入し、製品設計力の向上を目指す企業も増加している。
ECMには設計や製造以外に、品質管理や保守部門も関わるため、組織横断的な情報共有の仕組みを整えることが必要である。それによって、設計と製造部門で適切な情報伝達ができれば、品質低下を防ぐことができる。また、製品のバージョン管理によって最新版の共有ができていれば、保守にかかる確認の工数を減らすことも可能である。
サプライチェーン管理と連携し、必要な部品の調達や在庫管理といったプロセスの最適化に活かすこともできる。
か行
カーボンニュートラル
温室効果ガスの排出量と吸収量の均衡を図ることを「カーボンニュートラル」という。カーボンは炭素、ニュートラルは中立という意味であり、温室効果ガス(GHG)の代表的な要因である二酸化炭素のほか、メタン、フロンガス、一酸化二窒素などの排出量と吸収量を差し引いて「実質ゼロ」にすることで、地球温暖化に対応することが主要な目的。日本では2020年10月に菅元総理が所信表明演説で2050年までにカーボンニュートラルを実現することを宣言し、注目が高まった。2021年に開催されたCOP26では154カ国・1地域が2050年などの年限を決めてカーボンニュートラルの実現を表明するなど、カーボンニュートラルの実現は世界的な取り組みとして潮流が生じている。環境・社会・ガバナンスを重視して投資先を選ぶ「ESG投資」が投資トレンドとなっていることもあり、経済産業省はカーボンニュートラルの実現のための対応を国内産業の成長機会として捉えている。そのため、化石燃料をできるだけ使わない社会や産業構造への変革「GX(グリーントランスフォーメーション)」を、GXリーグやGX実現会議を設け、国を挙げて推進している。
2023年5月に経済産業省、環境省が発行した「カーボンフットプリント
ガイドライン」によると、サプライチェーン全体における温室効果ガスの製品単位の排出量(カーボンフットプリント:CFP)を見える化する仕組みが不可欠であるものと位置付けており、製品のライフサイクルを管理するPLMや製品情報を管理するPDMが重要な役割を担う存在といえる。
含有化学物質管理
含有化学物質管理とは、製品に含まれる化学物質の種類と量を把握し管理するプロセスで、法規制への対応や環境保護、人の健康を守ることを目的としている。近年は消費者や投資家から、環境と健康に配慮した製品を求められることが増えており、企業は化学物質の管理と透明性を高める必要がある。
含有化学物質管理には、サプライチェーン全体にわたる情報共有が必要であり、システムを活用する企業も多い。システムの機能としては以下が挙げられる。
調査受付管理
製品の納入先からの調査依頼を登録し、依頼内容を管理できる。また、回答データの作成といった報告機能を持つシステムも存在する。
調査依頼管理
仕入先に対し調査依頼データの作成や送付ができる。調査依頼の進捗管理や督促管理も可能。また、仕入先から送られた収集データの取り込みやエビデンスとなる文書も管理できる。
環境部品表管理
梱包材や副資材を含む、購入した材料の仕入先管理ができる。その際はBOM(部品表)と連携した環境部品表の登録も可能。
製品の集計と評価
製品や部品単位での含有化学物質情報の集計を行い、RoHS指令やREACH規則などへの対応状況の評価を行う。中には、規制と化学物質の対応マッピングができるシステムも存在する。
校正管理
校正管理は、計測機器や検査装置が正確な測定を行えるよう、定期的に精度を確認し、その記録や管理を行うプロセスである。校正では、計測機器の測定値を基準機の値と比較し、ズレが生じている場合には修理や調整を行い、機器を適切な状態に戻す。
校正結果は、校正証票に記録され、ISO9001の品質管理基準においても要求される重要な要素となる。
計測機器の精度が確保されることで、製造工程や品質管理において信頼性の高い測定結果が得られ、不良品の発生を抑えることができ、品質保証や製品の信頼性向上に欠かせない役割を果たしている。
関連リンク
コンフィグレータ
コンフィグレータは、顧客やユーザーが製品やサービスを自由に選択し、カスタマイズできる仕組みのことで、主に製造業や販売業界で利用され、個々のニーズや要件に合わせて製品を構築するためのツールやプロセスを指す。
この仕組みは、顧客が製品の特定の機能や仕様を選択し、それに基づいて製品が自動的に構築・設計されることを可能にする。部品の組み合わせの実現性を設計部門などの専門部門に確認することなく、リアルタイムに判断することができる。
コンフィグレータは見積もりのプロセスにも密接に関連している。顧客が選択した構成やオプションに基づいて、自動的に価格見積もりを生成することができる。これにより、迅速で正確な見積もりを提供し、顧客との信頼関係を強化される。
見積もりの過程では、顧客が選択したカスタマイズ項目や数量に基づいて、製品のコストを詳細に計算する。また、見積もりが確定した場合、それを元に発注や製造プロセスが始まる。コンフィグレータを組み込んだ見積もりプロセスは、生産性向上や正確性確保に貢献し、企業の競争力を向上させる要素となる。
さ行
サプライチェーン
サプライチェーン(Supply Chain)は、Supply(供給)とChain(連鎖)を組み合わせた造語であり、製品の調達・製造・流通・販売・消費・(回収)におけるモノ・カネ・情報などの一連の経路を鎖に見立てた「供給連鎖」という意味。サプライチェーンはメーカーや物流、小売りなど複数の事業者や関連会社が携わるプロセスも含まれているのが一般的だ。各工程における情報を適切に見える化し共有することで、サプライチェーンを構成するそれぞれの事業者が連携して全体の最適化を図ることを「サプライチェーンマネジメント(SCM)」という。サプライチェーンマネジメントに取り組むことで、災害や地政学的なトラブルによってサプライチェーンが寸断され製品を供給できなくなるといった「サプライチェーンリスク」に備えやすくなる。また、需要予測や在庫情報なども共有できるため、収益性やコスト削減にもつなげられる。さらに、多様な消費者ニーズや変化するビジネスモデルにも柔軟に対応しやすくなるため、各プロセスのグローバル化やIT化が激しい市場において重要な取り組みとなっている。
治工具管理
製造時に使用するさまざまな治具や工具、金型などを一元的に管理すること。治具とは、部品の固定や作業のガイドをする役割がある。工具にはドライバーのような作業工具のほか、切削加工や変形に用いられるものも含む。治工具が欠品すると生産ができず、治工具の不良があると製品の品質に影響するため、購入から廃棄までのライフサイクル全般にわたって、必要な在庫の確保と良好な状態の維持が必要である。
従来、治工具の保証や破棄は現場の担当者の感覚で行われることが多かったが、これらを紙の台帳で管理すると作業が煩雑化するだけでなく、ヒューマンエラーが発生するデメリットがあるため、治工具管理システムの活用を検討する企業が増えている。
治工具管理システムでは、治工具にRFIDタグなどを用いて治工具を個体認識し、台帳管理をすることが可能である。生産実績とのリンクも簡単に行えるため、適切な時期にメンテナンスや廃棄ができ、製品の品質管理や治工具の在庫管理にもつながる。
主に以下のような機能がある。
| 受入機能 | 治工具の発注受入、メンテナンス受入および検査 | |
| 装着機能 | 治工具の機械設備への配置、取り外しなどを管理 | |
| 寿命管理機能 | 治工具の消耗を管理し、再研磨・破棄を判断 | |
| 発注機能 | 治工具の新規発注およびメンテナンスの外部発注 | |
| 在庫管理機能 | 治工具の在庫状態および所在を管理 | |
| 実績管理機能 | 治工具の各種実績情報の検索 | |
| 治工具履歴追跡機能 | 治工具の使用履歴を追跡、不具合発生時の影響範囲の把握 | |
| 貸出予約機能 | 治工具の貸し出し・返却の予約と記録を管理 |
生産管理システム
生産管理システムとは、製造業における受注から生産、出荷に至るまでの生産プロセスを統合的に管理・共有を可能にするツールである。生産プロセスの効率化、最適化を目的としており、生産計画や在庫・工程・コスト(ヒト、モノ、カネ)を総合的に管理し、経営一体で管理する機能が含まれる。
生産計画
需要予測や販売計画、得意先の内示(見込み)情報を元に、1ヵ月から1年単位で生産計画の基本軸となる「大日程計画」を作成する。生産量に対して必要となる部材やリソースの所要量を算出するためのシミュレーションが行われる。
生産手配
所要量をシミュレーションした結果に基づき、範囲を確定することで、生産に必要な材料や部品の購入、生産ラインへ手配。手配の情報を元に、予定実績の管理を行い、円滑な生産活動の支援を行う。
原価管理
各種実績データを元に、製品の製造コストを積算し、生産にかかる各種コストを詳細に分析する。原価データを活用することで、最適な製造コスト、最適な販売価格の設定で、適正利益を確保する。原価データを分析することで、品質や新製品への反映、経営分析など、多角的に利用する重要なデータとなる。
在庫管理
日々の物の動きを、情物一致させることで、リアルタイムに受け払いを管理する。在庫情報に紐づく、製造日やロット、シリアル情報といった品質情報、ロケーション管理や棚番管理、パレット管理など、業態によって、在庫管理の形態は複雑になる。システムで正確に管理することが、過剰在庫や欠品を防ぐ第一歩となる。
購買管理
生産に必要な材料や部品の調達と供給をオーダーに合わせて、納期、数量、発注先、価格をシステムで管理し、円滑な調達運用を支援する。数量は、最低ロットなどマスターを参照して算出する。
進捗管理
工程毎の各プロセスにおける生産の予定・実績をリアルタイムで監視・管理する。生産の遅延や納期変更、不良率上昇などの問題点を迅速に特定し、品質・納期遵守に役立つ。近年、IoTの技術を使い、生産状況を一括で管理するケースも増えつつあり、製造業にとって、重要な管理となる。
このように生産管理システムは、DXを推進し市場の変化に迅速に対応する柔軟性や、効率化による競争力の向上を目指す製造業向けのシステムといえる。
製造原価
製造原価は、製品の生産に必要な費用の総称であり、主に材料費、労務費、そしてその他の経費が含まれる。これは、原価管理や利益計算において重要な基準となり、経営戦略の観点からもコスト削減や収益性の向上のための基盤となる。製造原価は、製品や生産活動に直接かかる「直接原価」と、工場全体の運営に必要となる「間接原価」に分けられる。
直接原価
直接原価は、製品や生産活動に対して直接的に発生する費用を指し、主に材料費や直接工の人件費が含まれる。直接原価の把握は、製品別の採算性や効率性を評価する上で重要となる。
間接原価
間接原価は、工場全体の運営に必要な間接的な費用であり、間接労務費や工場の光熱費、設備の保守費用などが該当する。間接原価の適切な割り当ては、製造コストの正確な把握や最終製品の価格設定の精度向上に寄与する。
設備総合効率(OEE)
設備総合効率(OEE:Overall Equipment Efficiency)は、製造設備の生産効率を評価するための指標。OEEは、設備の稼働状況や生産性を数値化し、「時間稼働率」、「性能稼働率」、「良品率」の3つの要素で構成される。これらを掛け合わせることで総合的な効率を算出する
設備総合効率は、次の式で表される。
| 設備総合効率=時間稼働率×性能稼働率×良品率 |
時間稼働率
計画された稼働時間のうち、設備が実際に稼働していた時間の割合を示す。この指標は設備のダウンタイムを減らすことで向上し、設備の安定稼働に貢献する。
性能稼働率
稼働している時間のうち、実際の生産スピードが理想的な生産スピードに対してどれだけ効率的であったかを示す。稼働の遅れや生産スピードの不安定さを改善することで、限られたリソースを最大限活用できる生産安定性を確保する。
良品率
生産された製品のうち、問題なく使用できる良品の割合を表し、製造プロセスの品質管理レベルを示す重要な指標。良品率が高いほど不良品の発生やリワークの発生が抑えられ、安定した品質の製品供給を実現し、生産計画への信頼性が高まる。
た行
デジタルツイン
デジタルツイン(DigitalTwin)とは、現実(物理オブジェクト)の情報を収集してデジタル空間(仮想空間)に再現する技術のこと。現実空間をデジタルで再現し、リアルタイムで情報を収集して反映できることから「デジタルの双子」とも訳される。デジタルツインの構築と現実空間との連携に必要な情報はエネルギー出力、温度、気象情報、人流などさまざまであり、センサーやカメラなどのIoT機器によって収集され、AIが分析・処理するのが一般的で、現実と極めて近しいデジタル空間でシミュレーションができるのが大きな特徴である。製造業においてはデジタルツインを活用することで、製品・製造にトラブルが発生した際のリアルタイムな原因の特定に役立てられるほか、効率的な試作による品質向上、開発コストの削減につながると期待されている。製造業の事例としてはアメリカの航空機エンジンメーカーがメンテナンスに用いている。また、ドイツの電機メーカーは自社製品のコンセプト設計から保守までをデータでつないだデジタルツインソリューションを提供している。
電気CAD
電気CADは、電気設備関連の設計に特化したソフトウェアで、電気回路や電気設備の設計・図面作成を効率的に行うための機能が充実している。電気CADを使用することで、単線接続図・屋内配線図・系統図といった電気回路や、端子図・板金図といった電気設備の図面をデジタル形式で編集でき、精度の高い設計が可能となる。電気専用のソフトは少なく、汎用CADソフトの追加機能として提供されることが多い。
電気CADの主な機能には、電気部品のライブラリや部品の配置や接続の最適化、図面間の連携が挙げられる。部品ライブラリでは、さまざまな電子部品やコネクタ、ケーブルなどを簡単に選択・配置することが可能。回路図・部品表・実装図の連携をすることで、設計変更があった場合に他の図面も自動で修正されるようになる。
汎用のCADソフトでも電気設備の製図は可能であるが、電気CADでは電気部品のライブラリを活用することで、複雑な専用部品の挿入が簡単になる。また、整合性を保つためのチェック機能を備えているため、設計ミスを早期に検出することが可能。このように作図工数や修正の回数を減らすことで、プロジェクトの効率と品質向上につながる。
トレーサビリティ
トレーサビリティは、各製品の原料調達から生産、物流、消費、廃棄までの一連の流れを追跡できることを表す用語である。この造語は、追跡という意味の「トレース(Trace)」と能力という意味の「アビリティ(Ability)」を組み合わせており、日本語では「追跡可能性」と訳すこともある。トレーサビリティは「チェーントレーサビリティ」と「内部トレーサビリティ」の2種類に大別でき、それぞれ目的や追跡する情報が異なる。
チェーントレーサビリティ
チェーントレーサビリティとは、原材料や部品の生産・供給から製造・加工、物流、販売、消費、廃棄・リユースといった全工程の履歴を追跡・遡及できる状態にすることを指す。主な目的はトラブルが生じた際の原因究明・対応(回収)などが円滑になり、消費者からの信頼性向上に繋げることである。
内部トレーサビリティ
内部トレーサビリティは、企業・工場ごと狭い範囲における部品や製品の移動を見える化することを指す。作業内容、検査結果といった部品情報を紐づけることで、生産・業務効率化や品質向上、歩留まりの向上、不良品の流出抑止などにも繋がる。
は行
フロントローディング
フロントローディングは製造プロセスにおいて、前倒しが可能な工程を初期段階で行うことである。初期工程にリソースを投じ、作業工程の前倒しをすることで修正回数を減らし、全体的な作業効率化とコスト削減を図ることを目的とする。
フロントローディングの要素として、主に以下の3つが挙げられる。
DR(デザインレビュー)
製品の設計段階で製造工程の担当者が集まり、不具合の可能性や効率的な製造方法について議論すること。設計者の意図を伝える場であるとともに、後工程の設計変更のリスクを減らすことができる。
検図
図面完成後に品質やコスト、期日、特許といった内容を検査すること。製品の品質確保だけでなく、コストや納期まで包括的に管理することが可能。
コンカレントエンジニアリング
製品開発において複数のプロセスを同時並行で進めること。たとえば、設計と生産準備を並行して進めることで、開発コストと期間を大幅に抑えることができる。
フロントローディングでは設計部門に負荷がかかるため、関係部門の協力や、製品ライフサイクルを俯瞰して管理できるPLM、3D CAD、シミュレーションソフトといったツールの活用により、設計部門の負担を抑えることも重要である。
ら行
ラインバランス
ラインバランスは、生産ラインにおける各工程の作業量を均等に保つことを指し、効率的な生産フローの実現するための手法である。ラインバランスの最適化を図ることで、生産の安定性と品質が確保され、工場全体の生産効率が向上する。
生産ラインバランス計画では、各工程の作業内容や所要時間を分析し、作業負荷を均一に分配する。ボトルネックや停滞が発生する工程を見極め配置や作業手順を調整することで、生産リードタイムの短縮や設備稼働率の向上につながる。さらに、適切なラインバランスを維持することで、製造原価の削減や納期遵守が可能となり、経営戦略の観点からも競争力の強化に寄与する。
関連リンク
A-Z,0-9
ALM
ALM(Application Lifecycle
Management、アプリケーションライフサイクル管理)とは、アプリケーションを構成するプログラムを開発する際に、企画から設計・開発・テスト・デプロイ・販売終了に至るまで、ライフサイクル全般を管理する考え方である。
専用のシステムを活用し、主にアプリケーション開発において、要件管理やプロジェクト管理、ソースコード管理、テスト管理、リリース管理といった内容を管理する。肥大化したシステム開発プロジェクトの可視性を高め、品質の向上や要件変更への柔軟な対応を可能としている。主な機能には以下が挙げられる。
| 要件管理 | ニーズの分析結果にもとづき、ソフトウェアの方向性を決定する | |
| ソフトウェア開発 | 共同編集や自動化の機能によって開発の効率化が可能 | |
| 品質管理 | 品質や使用状況を分析し、メンテナンスに活用する | |
| ソースコード管理 | ソースコードの変更について追跡および管理をする |
ソフトウェアライフサイクルにかかるコストの大半を占めるメンテナンスにおいて、設計段階から一貫した開発ができるALMは、コスト削減の有効な手段となる。また、近年は規制や規格・法令の変更に対応する重要性も増しており、ALMによる管理の必要性が高まっている。
BOM
BOM(Bill Of
Materials)は、製品を構成する部品や材料の一覧表で、製造現場の管理に活用される。1970年代初頭のアメリカで生産・在庫管理の手法として誕生し、1970年代後半に日本で普及した。複雑で部品の多い製品ほど、BOMシステムによる管理が重要であるといえる。
用途に応じてE-BOM(設計部門用)とM-BOM(製造部門用)などに分けられる。E-BOMは製品の構成やユニット構成を一覧にまとめたもので、M-BOMは組み立てや製造時に必要な情報(中間工程や副資材など)をまとめたものである。
ExcelなどによるBOMの運用は、情報を最新の状態に保つことが難しいため、製品設計の変更があった場合に製造コストの増加や品質の低下につながるリスクがある。PLMシステムやPDMシステムで一括管理をすることで、こうした課題に対処できる。
BOP
BOP(Bill of Process)の略語で、製品の組立や加工における部品ごとの工程・手順、それぞれを構成する情報を管理するための統合システムを指す。日本語では「製造工程表」と訳されることもある。BOPは製品の生産プロセスの情報を整理し、設計部門と生産部門のBOM連携をスムーズにする役割を果たし、開発期間の短縮や部門間の出戻り防止などが期待される。また、BOPは製造工程や設備、品質計画、製造条件はもちろん、作業時間、工程名など幅広い情報を統合管理し、製品設計・開発から生産プロセスの効率化を図り、コスト削減やグローバルな拠点の生産技術情報の管理の実現も期待される。
ERP
ERP(Enterprise Resource
Planning)とは、企業のあらゆる資源を統合的に管理し、業務プロセスを最適化するための手法またはシステムである。ERPによる効率化や経営状況の可視化を実現するために、多くの企業ではERPシステムを導入し、財務・人事・生産・在庫・販売データなどを管理している。
ERPシステムは基幹システムの一種で、異なる部門の情報や機能を統合して管理することが可能である。主に、企業の経営に欠かせない以下のような機能が搭載されている。
- 販売管理
- 購買管理
- 生産管理
- 原価管理
- 在庫管理
- 品質管理
- 財務管理
従来は部門別にデータ管理していたが、一元化することにより迅速かつ効果的な意思決定が可能になる。
製造業でERPを導入することによって、たとえば、販売部門の受注情報が自動的に生産計画や在庫管理システムに反映され、必要な資材の購入や生産スケジュールの調整がスムーズになるといった変化が期待できる。
さらに、最近では、請求や売掛、入金、仕入、買掛、支払などの販売管理機能を有する拡張性の高い生産管理システムを導入して、基幹業務を統合的に管理できるERPとして利用する企業もある。これにより、企業は製造と販売の両方のプロセスをより効果的に統合し、生産から収益化までの全体的な流れを効率化することも期待できる。
MES
MES(Manufacturing Execution
System、製造実行システム)とは、製造業における生産プロセスを管理し、効率化を図るための情報システムである。製造工程をリアルタイムで監視し、作業者への指示や品質、生産資源の配分といった内容を統合的に管理するため、生産現場にもっとも近い領域で活用されるシステムといえる。
具体的な機能については、MESA(Manufacturing
Enterprise Solutions Association)が11の機能を定義している。
| 生産資源の配分と監視 | 設備や作業者などを適切に配分し、状況を監視 | |
| 作業者管理 | 作業者に最適な作業を割り当てる | |
| 作業のスケジューリング | 生産計画をもとに詳細なスケジュールを策定 | |
| 製造指示 | 作業スケジュールをもとに製造指示や変更をする | |
| プロセス管理 | 生産状況を監視して異常発生時の作業者の対応を支援 | |
| データ収集 | 設備の稼働状況や作業者のデータを収集 | |
| 実績の分析 | 生産実績データから生産状況を分析 | |
| 設備の保守と保全管理 | 設備の保守や保全活動の計画を管理 | |
| 製品品質管理 | 品質データを収集して異常の有無を管理 | |
| 製品の追跡と製品体系の管理 | 生産途中の仕掛品の追跡管理 | |
| 仕様と文書管理 | 仕様書や作業手順書などの生産に必要な文書を管理 |
グローバル化にともない、生産現場には少量多品種生産やリードタイムの短縮が求められており、それらを実現するうえでMESは効果的な選択肢となる。
引用・参考元(外部サイト)
PDM
PDM(Product Data Management)は「製品情報管理」を表し、CADデータや図面、部品表(BOM)といった、製品や設計に関するデータを一元管理することである。データの一元化により、設計部門と他の部署との情報共有をスムーズに行うことができ、生産性の向上や品質向上、コスト削減などを実現できる。主な機能には以下の7つが挙げられる。
BOM(部品表)管理機能
BOM(Bill Of Materials)とは、製品を構成する部品・材料をまとめた一覧表。PDMでは、BOM管理が効率的に行える。
ドキュメント管理機能(図面、技術文書等)
製品設計生産プロセスで生成される図面や技術文書などの製品データを一元的に管理するための機能。部門を横断してドキュメント管理が行える。
変更管理機能
PDMの変更管理機能では、設計の改版履歴・版管理までが行え、最新版の把握やデータの復元なども容易に行える。
キーワード検索機能
製品の属性、ファイル名、プロジェクト名、部品番号などのさまざまなキーワード検索機能で、製品データベース内の情報を迅速かつ効率的に見つけることができる。
構成検索機能
部品・図面の親子関係をツリーで表示することができる。製品に使われている部品をツリーで表示や、特定の部品が使用されている製品の一覧表示も可能。
構成比較機能
構成比較機能とは、製品の2つの構成のうち異なる部分を把握するために使用する機能。部品の有無、全体の部品数や個々の部品の属性などが把握できる。
ワークフロー機能
設計現場の業務フローを可視化し、上位者への申請・承認管理が行える。現在の仕掛状況や査閲状況も確認しながら、ステータス管理も可能。
なお、PDMはPLMとしばしば混同されるが、PDMが製品データの管理に特化するものであることに対し、PLMはより多くの機能を備え、製品のライフサイクル全体をカバーすることができる。
PLM
PLM(Product Lifecycle
Management)は、「製品ライフサイクル管理」を表し、製品の企画から廃棄に至るまでの技術的な情報を一元管理することである。統合的に管理・分析することで、製品開発力や企業競争力を強化することがPLMの目的である。
そのほか、製品の品質向上やコスト削減、市場投入までの時間短縮を達成するためのフレームワークとしても機能する。
主な機能として以下の7つが挙げられる。
- プロジェクト管理
- BOM管理
- 工程情報管理
- 3D CAD管理
- 顧客レスポンス
- コスト管理
- リスク管理
PLMにより、設計や生産部門などで「BOM」「工程」「CAD」「顧客レスポンス」などの情報を共有・一元管理することで、生産効率の向上、不具合対応の迅速化、品質向上など、さまざまなメリットが生まれる。
2D CAD
平面図面の作成、または管理するためのコンピューター設計支援ソフトウェアの総称を2D CAD(2次元CAD)という。2D CADは製造、建築分野のほか、幅広い工業分野において主要な設計ツールであり、無料のCADから多彩な機能を備えたプロ向けまでさまざまな製品が普及している。2D CADは手書きでの作図と同様、正面図・平面図・側面図の三角法の視点をもって、縦横の2軸で角度や形状を表現する。2D CADは手書き作業と同じ感覚かつ手書きよりも修正・加筆が容易なことがメリットである。一方、近年、需要が高まっている3D視点への変換が難しく、図面を見慣れていない人は理解が困難であり、さらにファイル数が増加して管理が複雑化しやすいといった点が3D CADと比べると劣っていると考えられる。また、2D CADは3D CADよりも導入コストが安く、連携先の閲覧環境も整いやすいというメリットもある。3D CADを導入する企業が増加しているが、設計初期段階の構想設計などでは2D CADと使い分けられるケースが多い。
3D CAD
3D CADは3Dデータ(3次元データ)によるコンピューター設計支援ソフトウェア(CAD)の総称。CADは製造業界、建築業界など幅広い設計に用いられており、従来は平面に設計する2D CADが主流だった。しかし、より複雑な設計物を効率的に表現できるほか、設計図を見慣れていない人も直感的に形状を把握しやすい3D CADの導入を検討する企業が増加している。3D CADのモデリング手法は、形状作成履歴・設計根拠をもとにモデリングする「パラメトリックモデリング」と、作成履歴などを参照しない自由に形状を作り上げる「ダイレクトモデリング」の2種類に大別できる。また、3D CADは搭載する機能と価格によってハイエンドCAD、ミドルレンジCAD、ローエンドCADに大まかに分類できる。ハイエンドCADはもっとも歴史が長く多彩・精密な機能を搭載しているが価格帯も高く、主に製品部品点数が多い自動車業界などの製造業で使われてきた。ミドルレンジCADはハイエンドCADと比較すると機能が限定されているが、事業者向けとしても十分な機能を有しており、コストも抑えられていることから幅広い業種・事業規模で使用されている。ローエンドCADは無償~数万円の価格帯の3D CADを指す。事業者として製品設計を行うには、機能面や処理速度が足りない可能性があり、主に個人ユーザー向けやサブツールなどとして用いられることが多い。