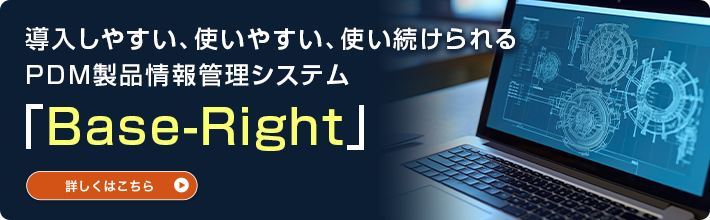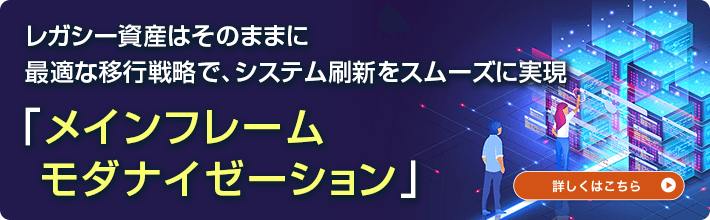ERPによるシステム統合で変わる!
運用コスト削減と業務効率化の具体的な方法
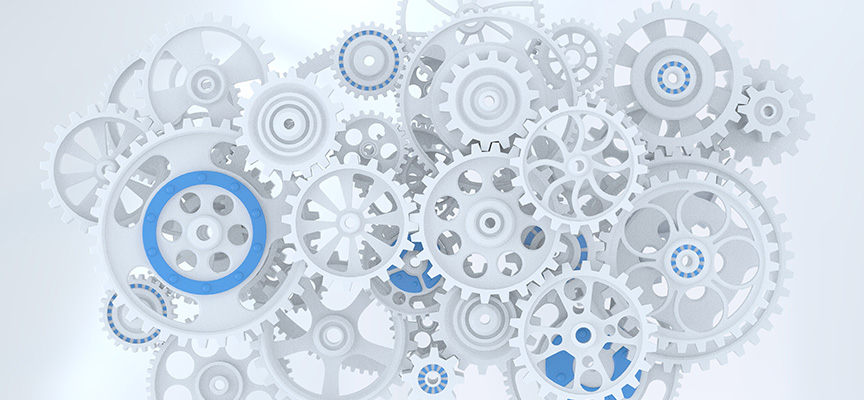
多くの企業では、長年の事業拡大や組織改編、あるいはM&Aや新規拠点の立ち上げに伴い、業務システムが部門や拠点ごとに個別導入されてきました。販売管理、生産管理、会計、在庫管理などが、その時々で最適と判断されたシステムとして導入された結果、全社的には「似たような機能を持つシステムが複数存在する」状態が生じ、運用コストの増加やデータの不整合、意思決定の遅れといった弊害が表面化します。特に、製造業や多拠点展開企業では、このような「システムの乱立」がサプライチェーン全体のスピードと精度を阻害し、結果的に競争力の低下を招く要因にもなっています。
本記事では、このような課題を解決するための手段として「ERPを活用したシステム統合」に焦点を当て、その効果と実現方法を分かりやすく解説し、運用コスト削減と業務スピード向上の両立へ向けた具体的なヒントをご紹介します。
目次

実例付きホワイトペーパー
真の業務標準化と全体最適で、「経営の型」をつくる製造業特化型クラウドERP「Infor CSI」の製品サイトはこちら
業務システムの分散により生じる課題
業務システムが部門や拠点ごとに分かれて運用されている状況は、一見、現場ごとに柔軟な運用ができるメリットがあります。しかし、企業全体の視点で見た場合、次のような深刻な課題を抱えることになります。
1. 運用・保守コストの増大
分散したシステムごとにライセンス料や保守契約、インフラ費用が発生します。たとえば、販売管理と生産管理が異なるメーカーの製品であれば、契約先もサポート窓口も異なり、更新や障害対応のスケジュールもバラバラになります。さらに、システムごとに専用サーバーやストレージ、ネットワーク設備が必要になり、ハードウェア保守費や更新費用も積み上がります。これにより、IT予算の多くが「現状維持」に割かれ、新しい投資をする余地が圧迫されます。
2. データのサイロ化と不整合
システムごとにマスタデータや取引履歴が独立して管理されることで、データのサイロ化(部門やシステム間でデータが分断されている状態)が発生します。商品コードや顧客コードがシステム間で異なる場合、突合や変換作業が必要となり、余計な手間が発生し、ミスのリスクも高まります。さらに、リアルタイムな連携が行われていないと、各システムで保持しているデータの更新タイミングがずれ、意思決定に古い情報が使われてしまう恐れもあります。
3. 業務スピードの低下
分散したシステムでは、情報を横断的に参照するために二重入力や手動でのデータ集計が発生します。たとえば、受注情報を販売管理システムに入力し、その後、生産管理システムに再入力するといった作業です。こうしたムダなオペレーションは時間を浪費するだけでなく、入力ミスによるトラブルを引き起こす可能性があります。その結果、見積作成や納期回答といった顧客対応スピードにも悪影響を及ぼします。
4. IT人材負担の偏り
各システムに精通した担当者が必要となるため、特定の個人に業務が集中し、属人化が進みます。担当者が異動や退職する際には、引き継ぎや再教育に時間を要し、運用上のリスクが高まります。
このように、分散したシステムは一見便利に見えるものの、長期的にはコスト、スピード、品質に悪影響を及ぼします。これらの課題を根本から解消するための手段が「ERPを活用したシステム統合」です。次章では、統合によって得られる主な効果を具体的に解説します。
業務システム統合による主な効果
分散していた業務システムを統合することで、企業は単なるIT環境の整理に留まらず、大幅な業務改善効果を得られます。ここでは、その代表的な効果を解説します。
1. 運用コストの削減
システムを統合すれば、サーバー・ライセンス・保守契約の重複を解消できます。これまで販売管理や生産管理、会計などで別々に発生していた保守費用や更新費用を一本化でき、契約や請求管理もシンプルになります。また、複数のインフラ環境を維持する必要がなくなるため、データセンター利用料やハードウェア更新費も削減できます。
2. データ精度の向上
統合システムではマスタデータが一本化され、常に最新かつ正確な情報が全社で共有されます。これにより、在庫数や生産進捗、売上実績といった重要データの信頼性が高まります。情報の食い違いによる社内調整や修正作業が減り、意思決定の精度も高まります。
3. 業務スピードの向上
統合されたシステムでは、データ入力が一元化されます。受注、在庫、生産、出荷といった一連の業務プロセスが1つのシステム上で連動するため、二重入力や手動でのデータ連携が不要になります。これにより、現場の事務作業時間が大幅に短縮され、顧客への納期回答や見積提示などのレスポンスも早くなります。
4. ガバナンスとセキュリティの強化
システム統合は、運用ルールやセキュリティポリシーの全社統一にもつながります。アクセス権限の設定や操作ログの管理が一元化されることで、不正利用や情報漏えいのリスクを低減できます。監査対応やコンプライアンス遵守も容易になり、経営管理の透明性が向上します。
5. IT人材の有効活用
運用対象が一つに集約されることで、IT部門の保守・運用負担が軽減されます。これにより、各システムに必要だった専門知識や個別のトラブル対応が不要になり、IT人材をより戦略的な業務改善やデータ活用にシフトさせることができます。
このように、システム統合は「コスト削減」と「業務スピード向上」の両方を同時に実現し、さらに組織全体の情報品質やガバナンスを強化します。次章では、この統合を成功させるための具体的な進め方をご紹介します。
成功するシステム統合の進め方
システム統合は、単に「古いシステムを新しいものに置き換える」作業ではありません。現状の課題を洗い出し、将来を見据えた全社的に最適な業務基盤を作るプロジェクトです。そのため、段階的かつ計画的なアプローチが不可欠です。ここでは、統合を成功させるための代表的なステップをご紹介します。
1. 現状分析と課題の可視化
まずは、自社が現在どのようなシステム構成になっているかを正確に把握します。
- 業務システムの一覧化(機能・利用部門・ベンダー・契約状況)
- 年間運用コスト(ライセンス・保守・インフラ費用)の棚卸
- 業務フローとデータ連携の流れを可視化し、二重入力や手作業の発生箇所を特定
この段階で課題を「見える化」することで、統合の目的や優先度を明確にします。
2. 統合方針の策定
次に、統合後の理想像と選定基準を定めます。
- 全社標準システムの条件(機能要件・業務適合度・拡張性)
- クラウド化かオンプレ継続かの判断
- 多拠点展開や海外対応の必要性
- 移行リスクや既存資産の活用方針
この方針が曖昧だと、統合後も部分的な最適に留まってしまうため注意が必要です。
3. 段階的な移行計画
一度に全業務を切り替えるのではなく、優先度や影響度の高い領域から統合を進めます。
- まずは在庫・販売・購買など、全社共通で影響が大きい領域を統合
- 並行稼働期間を設け、移行後の安定性を確認
- 部門間・拠点間の切り替えスケジュールを段階的に実施
これにより、リスクを抑えつつ、統合した効果を早期に実感できます。
4. 現場との連携と教育
システム統合は、IT部門だけで進めるものではありません。現場担当者が安心して新システムを使えるよう、トレーニングや説明会を通じて理解を深めてもらうことが重要です。
- 「なぜ統合が必要なのか」を共通認識として持つ
- 操作方法や業務フローの変更点を事前共有
- 移行テスト段階で現場のフィードバックを反映
現場を巻き込むことで、統合後の定着率の向上に繋がり、業務変革のきっかけとなります。
ERP統合で実現する全社最適化
全社最適の業務基盤を形成するためのシステム統合は、企業の競争力を強化する重要なステップです。ERPを活用した統合は、単なるITインフラの更新を超え、業務プロセスを革新し、組織全体での情報品質向上とコスト効率化を目指します。
これまでの業務システムの乱立による運用コスト増加やデータ不整合、意思決定の遅れなどの課題を解消することができれば、コスト削減と業務スピード向上といった効果が期待できます。統合プロジェクトの成功には、現状の課題の明確化、統合方針の正確な策定、段階的な移行、現場の協力を得ながらの推進が不可欠です。
本記事で紹介した具体的なステップを参考に、実践を通じて効果を実感し、企業の成長を支えるプラットフォームへとシフトしてください。今後の市場環境や事業戦略を見据え、分散したシステムからの脱却することが、次の成長ステージへの重要な一歩となるでしょう。

実例付きホワイトペーパー
真の業務標準化と全体最適で、「経営の型」をつくる