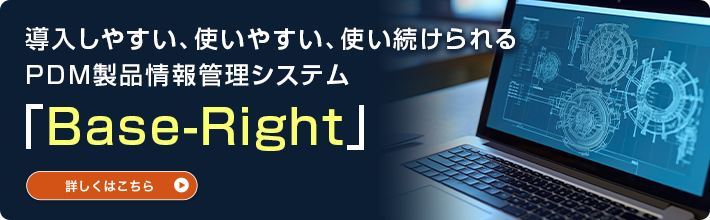PLM(製品ライフサイクル管理)とは?
PLMとPDMの違いを徹底解説

製造業の環境は国際競争の激化や顧客ニーズの多様化により、ますます厳しさが増しています。このような中、市場での競争力を維持するには、品質、コスト、納期(QCD)の向上が不可欠です。しかし、製品開発から生産、販売、アフターサービスに至るまで、多岐に渡る情報やプロセスを効率的に管理することはかんたんではありません。こうした状況を打破するカギとなるのが、「PLM(製品ライフサイクル管理)」と「PDM(製品情報管理システム)」です。
本コラムでは、製造業が抱える代表的な課題を整理し、PLMとPDMが果たす役割や効果を解説します。また、PLMとPDMの基本的な機能や効果についても説明し、企業のニーズに応じた最適なシステム選びのポイントを解説します。
Base-Rightの製品サイトはこちら
目次
PLM(製品ライフサイクル管理)とは?
PLMはProduct Lifecycle Managementの略語で、日本語では「製品ライフサイクル管理」を意味します。これは、企業が製品を開発する際に、初期のアイデアから製品の設計、生産、廃棄に至るまで、すべての製品やプロセスを統合的に管理する仕組みです。これにより、業務の効率化や生産性向上を図るとともに、製品開発のスピードや競争力を高めることができます。
現在、多くの企業がPLMの導入を検討しており、とりわけ製造業では、急速に変化する競争環境への対応策として注目を集めています。
PLMが注目される背景
PLMが注目され理由として、製造業を取り巻く環境変化と課題の深刻化が挙げられます。以下では、特に影響の大きい要因を整理します。
1.顧客ニーズの多様化
顧客の要求は年々高度化しています。ニーズの変化に迅速かつ柔軟に対応するため、製品プロセスの効率化とデータの一元管理が求められます。
2.国際競争の激化
グローバル市場での競争が激しさを増しています。製品の品質向上やコスト競争力を強化し、差別化を図る製品開発力が不可欠です。
サプライチェーンの複雑化
製品の多品種化により、品質・納期を確保する迅速かつ効率的な供給体制の構築が求められています。
これらの課題を克服するためには、製品ライフサイクル全体を俯瞰的に管理し、部門やプロセス間の連携を強化することが求められます。PLMは、品質(Quality)、コスト(Cost)、納期(Delivery)のいわゆるQCD向上を支える基盤として、多くの企業に採用されています。また、PLMとともに注目されるのが、設計データの効率的な管理を可能にするPDM(製品情報管理システム)です。
次章では、PLMとPDMの基本的な違いと、それぞれの役割について詳しく解説します。
PLM(製品ライフサイクル管理)とPDM(製品情報管理システム)の違いとは?
製造業では、QCD(品質、コスト、納期)の向上が競争力維持のカギとなっています。そのため、設計データや生産データなど多岐にわたる情報や、プロセスを効率的的に管理する為のシステムが不可欠です。PLMとPDMは、こうしたニーズに応える主要なソリューションとして注目されています。
一見似ているようですが、PLMとPDMには明確な役割と機能の違いがあります。それぞれの特長を以下で解説します。
PDM(製品情報管理システム)の概要
PDMは、製品の設計データや図面、仕様書などの情報を一元的に管理するシステムです。主に設計担当者やエンジニアリング部門によって更新され、部門間でデータが共有される仕組みになっています。データの更新や一元管理を適切に行うことで、流用設計や見積もりの再利用ができるようになり、設計業務の効率化が期待できます。
PLMとPDMの機能の違い
PLMは、製品のアイデア創出から廃止に至るまで、ライフサイクル全体を管理するシステムです。市場分析やリソースの管理、さらにはアフターサービス迄をカバーできる機能がそろっています。
一方、PDMは製品開発や設計段階のデータ管理を主な目的とし、CADデータやBOM(部品表)の管理、設計変更や版数の管理に特化しています。
PLMとPDMの効果の違い
PLMの導入は、各部門やプロセス間の横断的な連携を強化し、製品ライフサイクル全体を通じたQCDの向上を目指します。これにより、リードタイムの短縮やコスト削減、品質向上が期待できます。
一方、PDMの導入は、主に設計データの保存や検索、再利用、共有などのデータの利便性をを高めます。その結果、設計作業や設計データの活用の効率化に繋がります。
PLM(製品ライフサイクル管理)の機能・導入メリット
PLMは、製品開発・設計に特化したPDMとは異なり、設計から製造、販売、さらにはアフターサービスまで、製品ライフサイクル全体を網羅する機能を持っています。本章では、PLMの主要な機能と導入するメリットをご紹介します。
PLMの機能
PLMは多岐にわたる機能がありますが、ここでは特に重要な6つの機能を挙げます。
- プロジェクト管理
- BOM管理
- 工程情報管理
- 3DCAD管理
- 顧客レスポンス
- コスト管理
- リスク管理
まず、データの一元管理は設計や生産段階において、部門間やチーム内での情報共有に欠かせない機能です。設計・製造・サポートBOMなどの「BOM管理」の連携を行うことで、代替部品の調達も行いやすくなるでしょう。設計の更新情報や生産現場のデータなどは、部門間で共有されるようになっています。また、不具合が起きた際のデータは蓄積されており、統計情報をノウハウとして活用することも可能です。
PLMでは、顧客から受けたフィードバックや要望、クレームも管理できます。その為、次の製品開発や改良で反映させることで品質向上につながるでしょう。原価立案機能は設計工程や部品価格などサプライチェーンのデータを統合することで、戦略的な原価を提示できるものです。リスク管理機能は、適切なタイミングで販売・撤退できるようにサポートする機能といえます。
PLMを導入するメリット
製造業の企業がPLMを導入し適切に活用することで、主要なメリットは以下の3つがあります。
- 市場投入までの時間短縮
- コスト削減
- 製品品質の向上
情報の透明性と効率的なプロセスにより、製品の開発から市場投入までの時間を大幅に短縮でき、競争力を高めることが可能です。また、冗長なプロセスやミスを減少させることで、開発や生産コストを削減することができるでしょう。さらに、全体的なプロセスの可視化と統合により、製品の質を一貫して維持・向上させることができ、顧客満足度向上に寄与します。
PLM(製品ライフサイクル管理)の最新トレンド
多機能で製品ライフサイクル全体の管理ができるPLMは、近年は新たなトレンド技術も取り入れながら進化を続けています。最新の3つのトレンドについて、簡単にご紹介します。
SaaS型の普及
従来はオンプレミス型のPLMがメインでしたが、高コストかつ仕様が複雑という課題がありました。最近では、SaaS型のPLMが普及しており、初期投資のコストが抑えられ、利用デバイスに制約がないという点が強みになっています。また、企業のニーズや業務プロセスに合わせて機能を追加できる拡張性の高さも特徴として挙げられるでしょう。
基幹システム連携/API連携
製造業では、PLM単体だけでなく、基幹システムや生産管理システムなどとの連携が欠かせません。APIを活用することで、システム間でデータを自動転送でき、手作業によるデータ連携の手間を削減し、人的ミスの防止につながります。
たとえば、経営情報を統合する「ERP」とPLMを適切に組み合わせることで、最新の製品データを活用し、人的・物的・金銭的リソースをタイムリーかつ効率的に配分できます。
中堅・中小製造業向け生産管理システム「Factory-One 電脳工場」
販売・生産管理システム「FutureStage」クラウド版
IoT/AR
IoT(モノのインターネット)とAR(拡張現実)といった最新技術を取り入れたPLMも登場しています。たとえば、IoTデバイスからのデータを活用することで、生産現場の稼働状況や、製品の実際の使用状況をリアルタイムで把握することが可能です。また、AR技術を利用することで、製品設計や機能シミュレーション、修理手順の可視化などに活用できるため、今後さらに用途は広がると考えられます。
PLMのコストに懸念がある場合、PDMの導入も選択肢に
国際競争の激化や顧客ニーズの多様化が進む中、製造業にはさらなるQCDの向上が求められています。PLMは製品のライフサイクル全体を管理することで、情報共有や蓄積、顧客フィードバックの管理、原価計画、リスク管理といった機能を通じて、QCD向上を強力に支援します。製造から販売、廃棄までの情報を一元的に管理したい場合にはPLMの導入が適しています。PLM製品ライフサイクル管理システム「Windchill」をぜひご検討ください。
一方、設計データの管理や共有、検索、BOM管理、ワークフロー管理など、設計段階の効率化に特化したい企業にはPDMの導入がオススメです。PLMとPDMの最大の違いは、その機能範囲とコストです。PLMは幅広い機能を提供する一方で、導入や運用に伴うコストや時間も大きくなる傾向にあります。また、導入にあたっては資金だけでなく、運用を担う人材の確保も重要な要素となります。
PLMの導入が難しい場合は、NSWが提供するPDM製品情報管理システム「Base-Right」がオススメです。このシステムは高い拡張性を備え、企業の運用や業務プロセスに合わせた柔軟な構築が可能です。これまで100社以上のメーカーに導入され、コストパフォーマンスの高さでも評価を得ています。また、Base-Rightのワークフロー管理機能は、生産部門や品質部門とのシームレスな連携を実現し、業務全体の効率化を支援します。
製品情報の管理に課題を抱えている方は、PDM製品情報管理システム「Base-Right」の導入もぜひご検討ください。